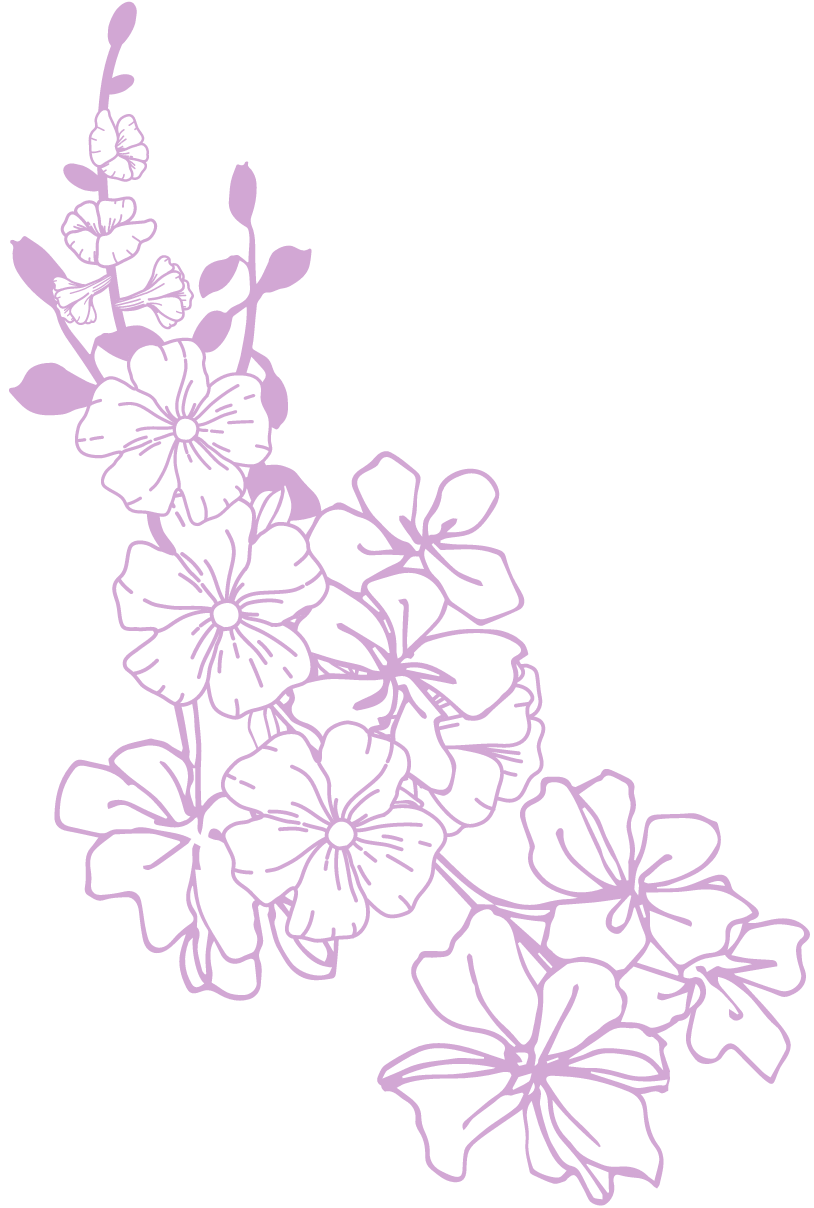子どもが歯医者を嫌がる理由を解説!「歯医者イヤ」を乗り越えて泣かずに通えるようになる為に親ができる安心サポートとは
Column
コラム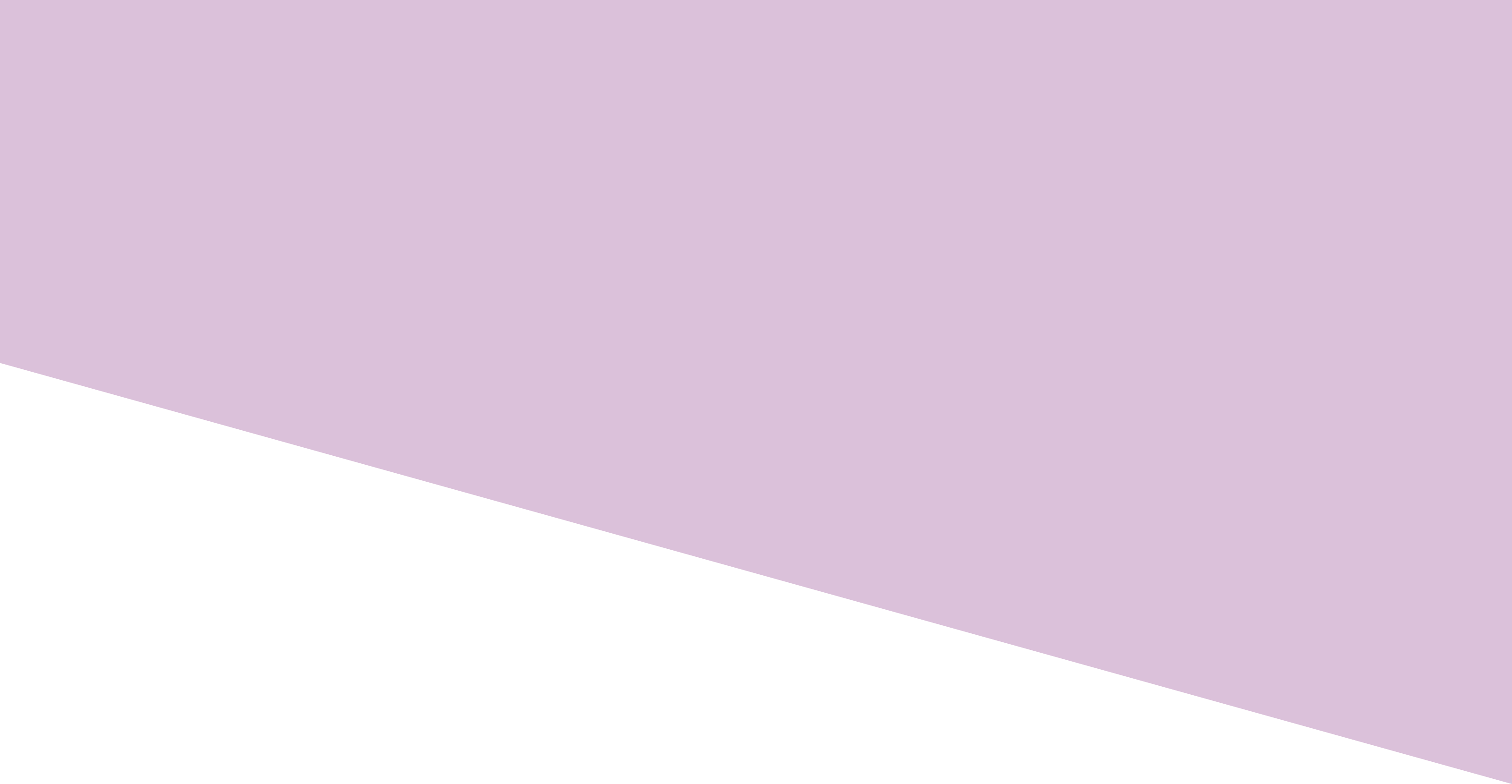
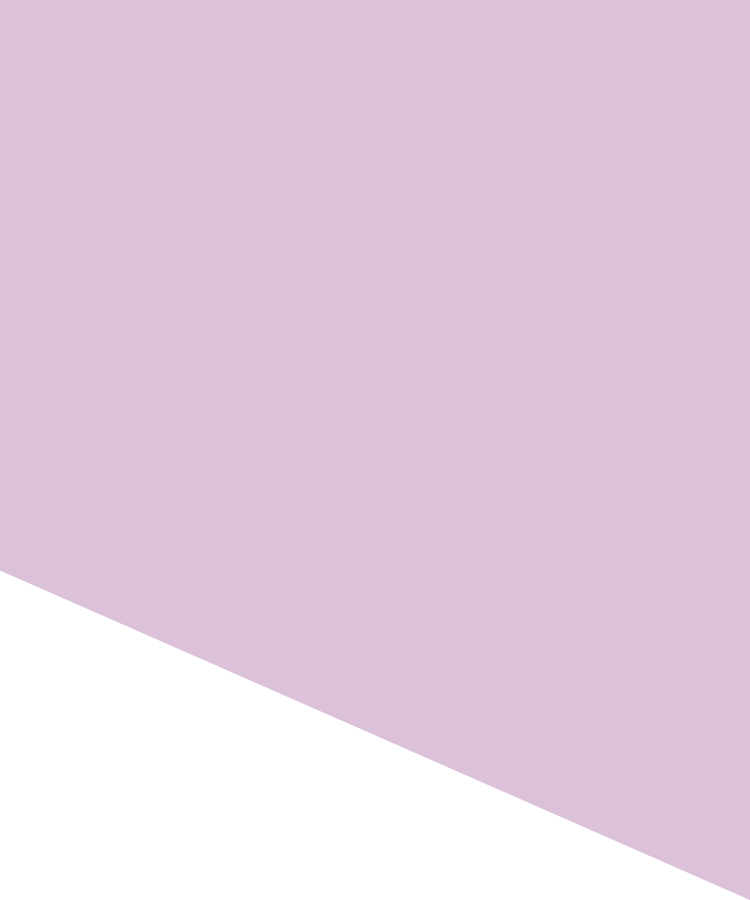

こんにちは。デュランタデンタルクリニック栄歯科・矯正歯科の歯科衛生士の國竹です☀️
8月に入り暑さも本格的になってきましたね💦
医院内の待合室にはウォーターサーバーを設置してますので、水分をしっかり補給して熱中症対策しましょう🚰!
今日は少し不思議な「口」と「腸」の関係についてのお話です。
私たちの身体には約500〜1000種類の数にすると約500〜1000兆個もの細菌がありそれらと共に生活をしています。
体内の細菌の質やバランスによって健康状態が変わってきますが、細菌が最も多く住んでいるのは「口」と「腸」です。
口と腸は一本の管で繋がっているので、口腔内に細菌が多いとそれを飲み込んで腸まで届き腸内環境が悪くなってしまいます。
つまり腸内環境をよくしたいのなら、口腔内の状態もよくしなければならないということです。
今回は「口の腸のつながり」について説明していきます!
口の細菌叢のことを口内フローラ、腸の細菌叢のことを腸内フローラとよびます。
「フローラ(Flora)」という言葉は、細菌の集団を顕微鏡で見た時にお花畑のように見えることからこのような名前がついています。
体の細菌は大まかに分けて3種類あります。
・善玉菌
・悪玉菌
・日和見菌
それぞれの菌が占める割合は人によって異なり、善玉菌の割合が多い人ほど健康で、悪玉菌が多い人ほど身体の健康上のトラブルをおこしやすくなります。日和見菌は最も高い比率を占める細菌ですがどっちつかずの細菌で、健康な時には悪さをせずおとなしい菌ですが、健康状態が悪い時には暴れ出します。
この3種類の菌のバランスは「善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7」が好ましいバランスとされています。
口腔内細菌の代表的な悪玉菌としては、
・ミュータンス菌(虫歯を引き起こす菌)
・P.ジンジバリス菌(歯周病の原因となる菌)
などがあります。
悪い菌を抑えるような働きをする善玉菌なども存在しており口の中も細菌のバランスによって健康が保たれています。
口と腸は遠い位置にありますが、一つの管でつながっています。私たちは日常生活の中で1日に約1兆もの口腔内細菌を飲み込んでいると言われています。
例えば、口腔内フローラの状態が悪玉菌優勢で、その細菌が食道を通り腸に到達した時にほとんどは胃酸や胆汁酸などで多くの細菌は死滅しますが、一部の細菌は生き残って腸内フローラのバランスを崩してしまうことがわかっています。
特に最近注目されているのが、先ほど口腔内細菌の種類で説明した歯周病の原因となるP.ジンジバリス菌です。
この菌が腸に入り込むことで、
・腸のバリア機能の低下
・免疫力が低下し、全身的な炎症を起こす
・腸内の善玉菌を減少させる
・感染症にかかりやすくなる
といった作用が確認されており、腸内フローラの乱れや慢性炎症の原因になり得ることがわかっています。
さらに、歯周病菌が増えやすい環境となり口内フローラの状態も悪くなります。
口から腸、腸から全身へといったように細菌の流れは全身の健康にも関係してきます。
腸は私たちにとって栄養素を吸収する場所である大事な臓器の一つです。
腸内フローラが悪化するとメタボリック症候群や糖尿病の悪化、免疫のバランスが崩れることでアレルギーや自己免疫疾患のリスクが上がる、うつ病や不眠、認知機能の低下にまで関わってきているという報告もあります。
また口内フローラの悪化はお口のトラブルだけにとどまらず
口内フローラの悪化で歯周病菌が増えると、歯周病を発症しやすくなり、それらの菌が全身に回り始めます。
そうすると心臓病や動脈硬化、脳梗塞、糖尿、早産・低体重児出産というような全身疾患を引き起こす可能性があります。
つまり、お口の中をきれいにし健康を保つことが「全身の健康」につながっているということです。
私たち現代人の体内菌のバランスはさまざまな原因によって乱れていて善玉菌自体が少なくなっていると言われています。
ファストフードや食品添加物の摂取が増えることで悪玉菌を増やしていると言われています。アスパルテームやスクラロースなどの人工甘味料も腸内環境に悪影響を及ぼすと言われており、腸内環境のエサとなる食物繊維の不足も善玉菌が減少する原因となります。
ストレスは自律神経を乱し、腸の働きを低下させ、睡眠の質が悪いと腸内環境の修復が間に合わず悪化します。
除菌殺菌製品の多用により、体に必要な常在菌まで減少する可能性があります。また幼少期から菌との接触が少ないと免疫系の発達にも影響があるとされています。
腸内フローラと口内フローラを健康に保つためには、生活習慣の見直しがカギになります🔐
【腸内フローラ改善のポイント】
・食物繊維や発酵食品(納豆、味噌、ヨーグルトなど)を積極的に摂取する
・加工食品や糖の過剰摂取を控える
・ストレス管理と良質な睡眠
・運動不足解消
【口内フローラ改善のポイント】
・歯科医院での定期的なメンテナンスで口腔内を清潔に保つ
・唾液の分泌を促す
今回は「口」と「腸」についてのコラムを書いてみました。
口と腸は離れた存在のように思えますが、実は一本の消化管でつながっており最近の流れも一方通行ではありません。
お口の状態が腸の環境を左右し全身の健康に関わります。
口と腸の関係を知るだけでメンテナンスの重要性をさらに感じられますね☺️
定期的なメンテナンス、歯医者にしばらく行ってないなぁという方も今日から”お口と腸のWケア”始めてみませんか?🪥✨
この記事の監修者

デュランタデンタルクリニック栄歯科・矯正歯科
院長坂本 果歩
地元の大分県の大分県立大分上野ヶ丘高等学校卒業後、
愛知学院大学歯学部歯学科に進学、卒業しました。
その後、愛知学院大学附属病院での研修を経て、愛知県内の地域密着型の医院、都心型の医院で勤務することによりたくさんの治療のスキルを学びました。
歯周病治療に力をいれた、再治療の少ない治療を目指して口腔外科、インプラント、矯正などの幅広い診療も行っています。
学歴・経歴
2016年 愛知学院大学歯学部歯学科 卒業
2017年-2018年 愛知学院大学附属病院 勤務
2018年-2023年 愛知県内 歯科医院 勤務
2021年-2022年 藤田医科大学 口腔外科 研究生
2022年 名古屋市 歯科医院 分院長
2023年 デュランタデンタルクリニック栄歯科・矯正歯科開業
現在に至る
所属団体
日本臨床歯周病学会
日本口腔インプラント学会
愛知インプラントインスティチュート
日本抗加齢医学会
日本歯科医師会
愛知県歯科医師会