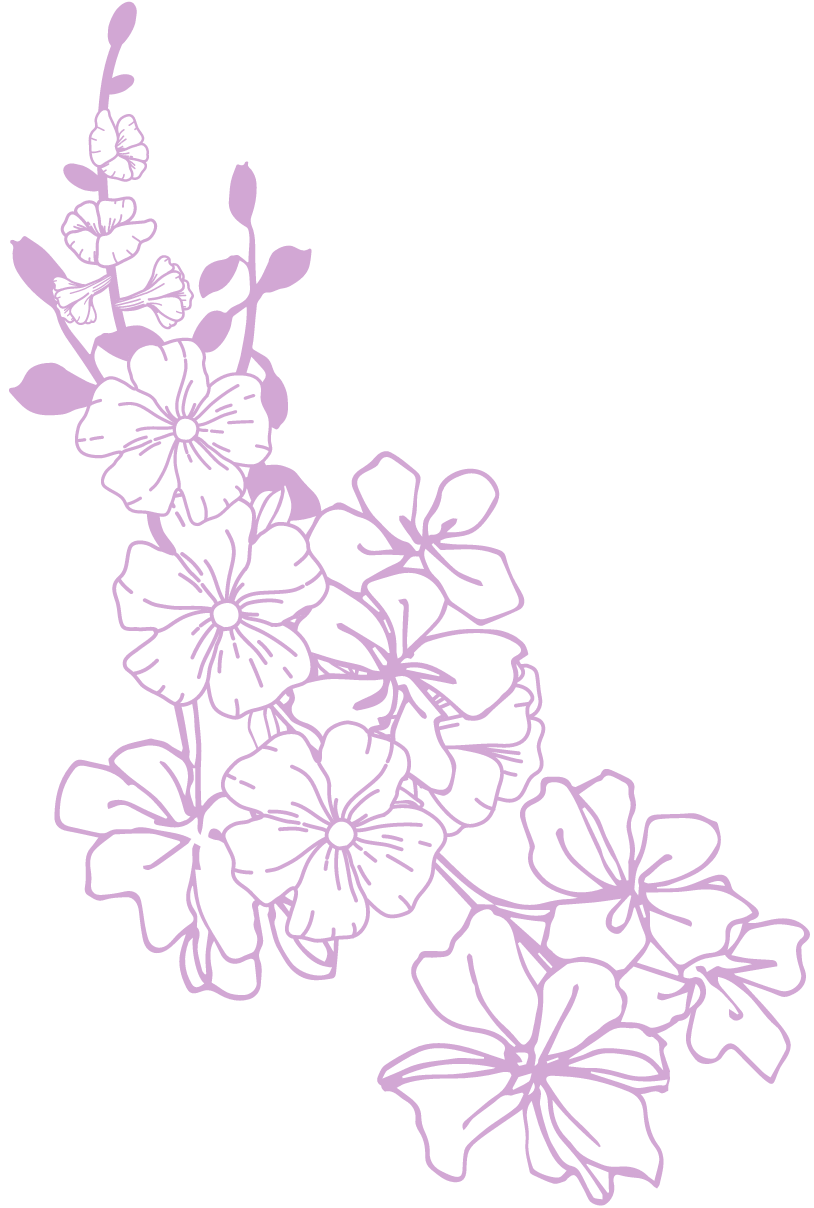子どもが歯医者を嫌がる理由を解説!「歯医者イヤ」を乗り越えて泣かずに通えるようになる為に親ができる安心サポートとは
Column
コラム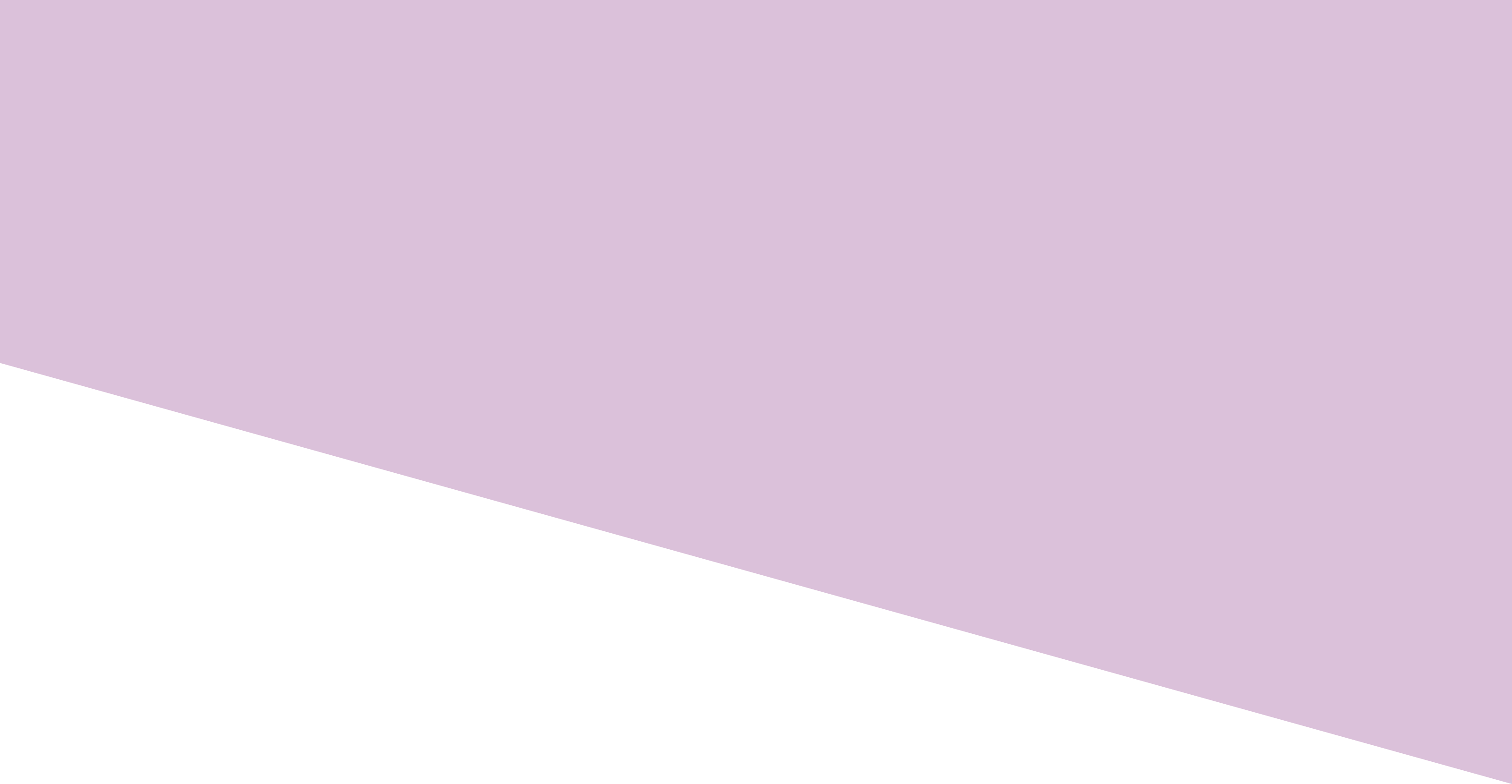
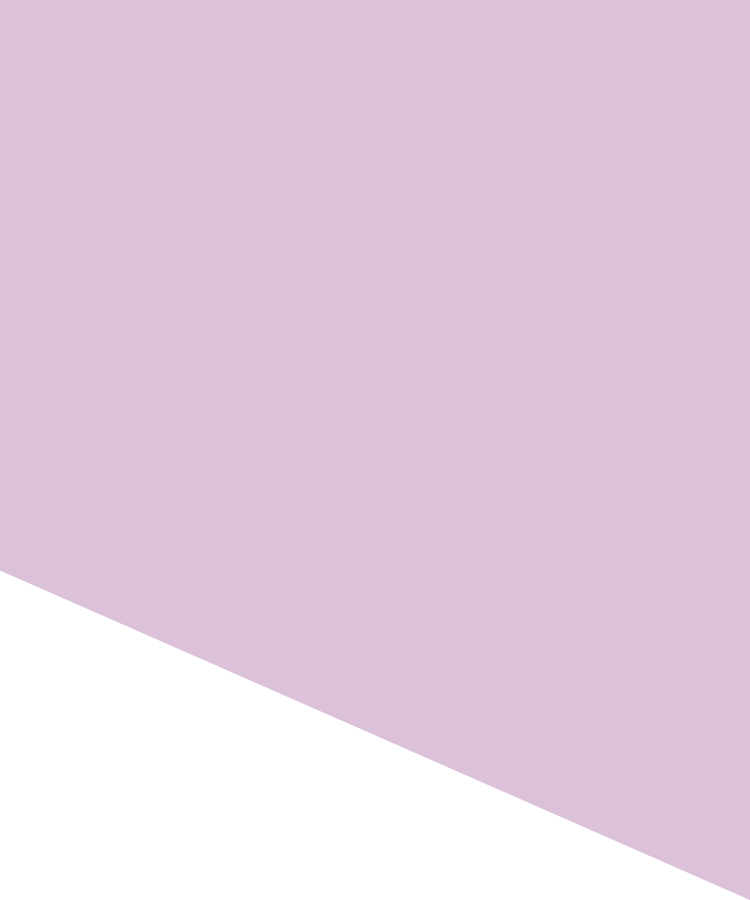

こんにちは。デュランタデンタルクリニックの歯科衛生士の井尾です。
いきなりですがクイズです。「体で一番汚い場所」ってどこだと思いますか?お尻?足の裏?実は……口の中なんです!びっくりですよね。
「体で一番汚い場所はどこ?」と聞かれたら、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは“お尻”や“足の裏”だと思います。けれど医学的に見ると、意外にも答えは口の中なんです!食べ物の残りかすや糖分がたまり、温かく湿った環境は細菌にとって最高の住処。なんとその種類の豊富さは大腸をもしのぐといわれています。でも安心してください。細菌が多い=不衛生というわけではなく、むしろ私たちの消化や免疫を支える大切な存在でもあるのです。
前回のコラムで口腔内細菌が腸内環境を悪化させる話をしましたが、今回もう少し詳しく細菌についてもお話ししていきますね😊
口の中は、食事のたびに糖分やタンパク質、脂質などの栄養源が入り込む場所です。特に糖分は、ミュータンス菌と呼ばれる虫歯の原因菌の大好物。糖を分解して酸をつくり、その酸が歯のエナメル質を溶かして虫歯を起こします。また、歯と歯の間や歯ぐきとの境目は食べカスがたまりやすく、磨き残しによって細菌が増え、歯垢(プラーク)や歯石の原因となります。
人間の口の中は平均で36〜37℃前後、湿度もほぼ100%に近い状態です。これは細菌にとって最高の繁殖環境。さらに、唾液には食べ物の残りカスや上皮細胞が混ざっていて、細菌の栄養源になります。
ただし、唾液には自浄作用(洗い流す力)や抗菌作用もあり、口腔内の環境を守る役割も担っています。つまり「唾液は細菌のエサにもなるが、細菌を抑える働きもある」という両面性があるんです。
大腸には膨大な腸内細菌がいて、総数は100兆個以上ともいわれます。ただし「種類の数」で比べると、口腔内には500〜700種類の細菌が住みついており、大腸よりも多いとされる研究もあります。
この中には、
・善玉菌(常在菌) … 消化を助けたり、病原菌の増殖を抑えたりする
・悪玉菌 … 虫歯菌、歯周病菌、口臭の原因菌などが存在し、バランスを取って共生しています。
・ミュータンス菌(Streptococcus mutans)
糖質(主に砂糖)を原料に不溶性グルカンという粘着性物質を作り、歯の表面に付着する性質があります。
・ラクトバチルス属(Lactobacillus)
酸に強く、進行した虫歯の中で増える。虫歯を悪化させるタイプ。表面がツルツルした歯には付着しにくいですが、他の菌が作り出した不溶性グルカン表面に付着し、虫歯の進行とともに増えると言われています。
・ソブリヌス菌(Streptococcus sobrinus)
酸素や糖がない環境下でも、虫歯の原因となる酸を作り出す菌です。ミュータンス菌以上に、歯に付着するための不溶性グルカンを形成する性質があります。ミュータンス菌だけを保持しているよりもソブリヌス菌も保持している人の方が虫歯になりやすいといわれています。
・ポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)
歯周病の“親玉”と呼ばれる菌。最も歯周病に関わりのある細菌であり、歯周病独特の悪臭の元となる内毒素を出します。歯ぐきの炎症や歯を支える骨を溶かして歯をぐらつかせます。口内の他に、気道・結腸・上部消化管にも生息しています。
・トレポネーマ・デンティコーラ(Treponema denticola)
スピロヘータというらせん状の菌。炎症を悪化させる、免疫抑制作用に関係してるとされ、重度歯周病の方で検出頻度が高いとされています。運動能力が高く、血管内にも入り込んで増殖することができ、心臓冠状動脈疾患部や動脈瘤から検出されることもあります。
・タネレラ・フォーサイシア(Tannerella forsythia)
歯周病の重症化に関与。ジンジバリス菌やデンディコーラ菌とともに、歯周病や根尖性歯周炎を悪化させるおそれがあるとされています。内毒素を持ち蛋白分解酵素も作ります。
・歯周病菌が血管に入り込むと、動脈硬化を進める物質をつくり、血管の内側を傷つける
・結果として 心筋梗塞・狭心症・脳梗塞 のリスクが高まる
・歯周病の炎症で出る物質が インスリンの働きを妨げる
・糖尿病が悪化しやすくなる
・逆に、血糖コントロールが悪いと歯周病も進行しやすい → 悪循環
・汚れた唾液や細菌が 気管に入り込むと、誤嚥性肺炎 を起こす
・高齢者の死亡原因の上位に入る病気
・妊婦さんが歯周病を放置すると、炎症物質が血液に流れ出して早産や低体重児出産のリスク を高めると報告されている
・歯周病菌が出す毒素が脳に影響して、アルツハイマー型認知症を進める可能性 があると研究されている
・口の中の細菌や毒素は血流に乗って体中に広がる
・結果、慢性的な炎症体質 をつくり、全身の病気のリスクを底上げしてしまう
口の中に細菌が多いからといって、それが即「不衛生」や「不健康」を意味するわけではありません。むしろ細菌がいなければ、人間の体は正常に働きません。
・消化のサポート:食べ物を分解して消化を助ける
・免疫のトレーニング:細菌が常に存在することで免疫システムが鍛えられる
・感染防御:善玉菌が病原菌の居場所を奪い、増殖を防ぐ
つまり「細菌が多い=悪」ではなく、「細菌のバランスが崩れること」が問題なのです。
では、どうすれば口の中を清潔に保てるのでしょうか。基本は毎日の歯磨きです。食後に丁寧にブラッシングを行うことが大切です。特に夜は、就寝中に唾液の分泌が減り細菌が増えやすいため、入念に磨く必要があります。
さらに、舌の表面にたまる舌苔のケアも欠かせません。専用の舌ブラシで優しく清掃することで、口臭予防に効果的です。また、デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間を清掃することも重要です。歯ブラシだけでは6割程度しか汚れが取れないとされており、補助的なケアでようやく8〜9割まで清掃できるといわれています。
加えて、定期的な歯科検診も忘れてはいけません。専門的なクリーニングを受けることで、自宅では取り切れない歯石やバイオフィルムを除去でき、口腔内の環境をリセットできます。
食生活も大きく関係します。糖分の多い食べ物や飲み物を頻繁に摂取すると、虫歯菌が酸をつくり出し、歯を溶かす原因になります。間食を控え、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。
また、ストレスや睡眠不足、喫煙も口腔環境を悪化させます。唾液には自浄作用がありますが、ストレスや喫煙によって分泌が減ると、細菌が増えやすくなるのです。
口腔内は細菌にとって最適な環境であり、「最も汚い場所」とされます。しかし、その細菌たちは私たちの消化や免疫に欠かせない存在でもあります。問題は“数”ではなく“バランス”。口腔内環境を整えることは、虫歯や歯周病の予防だけでなく、全身の健康リスクを減らすことにもつながります。日々のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアで、健やかなお口と体を守っていきましょう☺️✨
この記事の監修者

デュランタデンタルクリニック栄歯科・矯正歯科
院長坂本 果歩
地元の大分県の大分県立大分上野ヶ丘高等学校卒業後、
愛知学院大学歯学部歯学科に進学、卒業しました。
その後、愛知学院大学附属病院での研修を経て、愛知県内の地域密着型の医院、都心型の医院で勤務することによりたくさんの治療のスキルを学びました。
歯周病治療に力をいれた、再治療の少ない治療を目指して口腔外科、インプラント、矯正などの幅広い診療も行っています。
学歴・経歴
2016年 愛知学院大学歯学部歯学科 卒業
2017年-2018年 愛知学院大学附属病院 勤務
2018年-2023年 愛知県内 歯科医院 勤務
2021年-2022年 藤田医科大学 口腔外科 研究生
2022年 名古屋市 歯科医院 分院長
2023年 デュランタデンタルクリニック栄歯科・矯正歯科開業
現在に至る
所属団体
日本臨床歯周病学会
日本口腔インプラント学会
愛知インプラントインスティチュート
日本抗加齢医学会
日本歯科医師会
愛知県歯科医師会